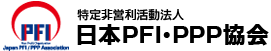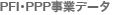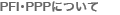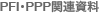PFI・PPP関連ニュース
▽2025.6.27
内閣府民間資金等活用事業推進室/PFI評価や性能発注促進へ/指標連動方式の考え方改定
内閣府民間資金等活用事業推進室は、PFI事業を対象とした「指標連動方式に関する基本的考え方」の改定版を公表した。今回の改定では、類似する方式との違いを整理するとともに、インセンティブの事例を追記している。事業コストの削減にとどまらず、PFI事業の価値向上を目指す性能発注を促すのが狙いである。改定版では、同方式の対象となる公共施設について、利用者から料金を徴収しない施設と明記し、サービス購入型PFIや包括的民間委託を導入しやすい事業に位置付けた。この方式は、管理者が求めるサービス水準に対応した指標を定め、その達成状況に応じて対価を変動させる仕組みである。情報元:建設工業新聞
内閣府/LABV方式で解説書/基本スキームや事業の類型
内閣府民間資金等活用事業推進室は、官民共同事業体(LABV)方式の解説書を公表した。LABV方式は、地方自治体などが土地といった公有資産を現物出資し、民間事業者と共同で開発プロジェクトを進めるPPPの一手法として定義されている。解説書では、基本的なスキーム、事業の類型、自治体や民間事業者のメリットなどを整理している。先行事例として山口県山陽小野田市の事業をモデルに挙げ、事業を成功させるには、将来の不確定要素を許容する「『決まっていないことを可』とする従来思考からの転換」が重要だと指摘している。遊休地の有効活用や地方創生のツールとして期待される同方式の普及を進める方針だ。情報元:建設工業新聞
国土交通省/適切な更新投資推進/官民で一体的再構築/国交省・上下水道/政策在り方検討会
国土交通省は「上下水道政策の基本的なあり方検討会」の第1次取りまとめを公表した。強靭で持続可能な上下水道の実現に向け、国主導による経営広域化の加速化、更新投資を適切に行う経営へのシフト、官民共創による上下水道の一体的な再構築の3点に取り組む。事業体に対し国の方針や効果を明確に示して意識改革を促すとともに、都道府県にはけん引役としての役割を期待している。今後は、質の高いウオーターPPPを推進し、経営広域化や適切な更新投資を行う上での公費負担の在り方も検討する方針である。将来的には、ウオーターPPPや脱炭素などの社会的要請をテーマに協議し、今後10年程度の上下水道政策の方向性を段階的に取りまとめる。情報元:建設通信新聞
▽2025.6.24
国土交通省/群マネ/実装の「手引」今夏公表
国土交通省は「地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)」の全国展開に向けた「手引」の骨子案をまとめた。夏ごろに公表する「Ver.1」では、群マネ導入の標準的なステップや先行事例のノウハウを周知する。これには、初めて取り組む地方自治体向けの「支援ツール集」や、全自治体のインフラメンテナンスの実態を「見える化」したデータも含まれる。自治体に自らの立ち位置を客観視させ、危機感を喚起しつつ、群マネへの理解と実装を促すのが目的である。従来の包括的民間委託の領域を超えた「広域連携」や「多分野連携」のパターンも解説される。将来の「Ver.2」では、契約上のインセンティブや広域連携スキームの構築方法も盛り込む予定である。情報元:建設工業新聞
▽2025.6.20
国土交通省/3分野で10件採択/官民連携モデリング事業
国土交通省は、2025年度の「民間提案型官民連携モデリング事業」に10件の提案を採択した。この事業は、地方自治体が抱える課題に対し、民間提案に基づく新たな官民連携手法を構築し、横展開する取り組みである。今回は33件の応募から選定された。採択された提案の内訳は、「戦略的なインフラマネジメントを担う自治体の体制確保」が5件、「スモールコンセッション」が3件、「グリーン社会」が2件である。採択案件には、インフロニアなどが提案した「データに基づく実態的広域化の検討」や、阪急コンストラクション・マネジメントによる「CM方式を活用したスモールコンセッションによる大型町家群再生利活用推進」などが含まれる。情報元:建設通信新聞
国土交通省/官民連携基盤整備/推進調査費を募集/国交省、PPP/PFI/可能性検討調査など補助
国土交通省は、2025年度「官民連携基盤整備推進調査費」の第3回募集を開始した。7月25日まで受け付ける。この制度は、民間事業と一体的に実施される地方自治体の基盤整備調査を支援するもので、補助率は2分の1以内である。対象は道路、河川、港湾、公園などの調査検討業務で、概略設計やPPP/PFI導入可能性調査などの委託費を一部補助する。コンセッション方式には特別交付税の措置もある。2025年度の重点項目として「PPP/PFI導入可能性検討調査」と「広域的な観光又は交流拠点形成の促進に係る調査等民間投資の誘発効果の高い調査」を設定している。情報元:建設工業新聞
▽2025.6.19
経済産業省/工業用水道事業費補助/中長期計画の策定を要件に/産構審小委が了承
経済産業相の諮問機関である産業構造審議会の工業用水道政策小委員会は、工業用水道事業者が国の補助金を申請する際に、インフラの更新需要などを盛り込んだ中長期計画の策定を要件とすることを了承した。これは、PPP/PFI導入のための補助や強靭化に関する事業が対象となる。経済産業省は事業者の計画策定を支援するためにチェックリストを公表する。また、PPP/PFIの導入を一層促進するため、同小委員会の傘下に専門家で構成されるワーキンググループ(WG)を新設し、官民連携に消極的な事業者への支援策やウォーターPPPの推進、広域化などについて議論し、2025年度内に具体的な取り組みをまとめる方針も決定した。情報元:建設工業新聞
内閣官房/水害/途上国のリスクマップ作成/内閣官房 G空間行動プラン
内閣官房の地理空間情報活用推進会議が、「地理空間情報の活用推進に関する行動計画(G空間行動プラン)2025」を策定した。今回のプランでは、新たに「国際展開」を政策パッケージに追加し、日本の地理空間情報技術を活用して途上国の発展に貢献する方針を明記した。具体的には、東南アジア4カ国で水害リスクマップを作成するほか、3D都市モデル「プラトー」を活用して都市デジタルツインの構築を支援する。また、防災分野では、国の新総合防災情報システム(SOBO-WEB)と地方自治体、民間企業などとの官民連携による情報共有を推進し、災害時の迅速な意思決定に役立てる。建設分野ではi-Constructionの推進による生産性向上も盛り込まれた。情報元:建設工業新聞
▽2025.6.16
国土交通省/来月25日まで募集/国交省の官民連携/基盤整備調査費
国土交通省は、2025年度第3回「官民連携基盤整備推進調査費」の案件募集を7月25日まで実施する。この調査費は、民間と自治体が連携して取り組むインフラ整備の事業化検討を支援するものである。対象は、国交省所管の道路、港湾、河川、公園などの社会資本整備事業の事業化に向けて、自治体が実施する概略設計や基礎データ収集、整備効果検討などの調査や、PPP/PFI導入可能性検討調査である。これらの調査にかかる費用の2分の1を補助する制度となっている。情報元:建設通信新聞
▽2025.6.11
国土交通省/7月7日、8日にPPP/PFI研修/自治体首長らが登壇/次世代に成功事例など伝える
国土交通省は「次世代を担う組織・人材のためのPPP/PFI研修」を7月に2回開く。いずれもウェブ方式で「ボトムアップ編」を7月7日、「トップダウン編」を同8日に実施、開始時間は両日とも午後1時30分である。有識者による講義のほか、過去に官民連携を成功させた首長や職員らによるトークセッションを行う。対象者はボトムアップ編が担当者クラス、トップダウン編が幹部職クラスである。申し込み締め切りはボトムアップ編が同1日、トップダウン編が同2日である。情報元:建設工業新聞
国土交通省/国主導で経営広域化/上下水道政策在り方検討会/多様な効果期待
国土交通省は日、上下水道政策の基本的なあり方検討会の第5回会合を開き、第1次取りまとめ案を審議した。案では強靱で持続可能な上下水道を実現するため、国主導による経営広域化の加速化や更新投資を適切に行う経営へのシフト、官民共創による上下水道の一体的な再構築に取り組む方針を示した。経営広域化を進めることで執行体制の強化、経営規模の拡大、一元的なマネジメントが図られ、事業体や住民、産業界に多様な効果が期待できるとした。情報元:建設通信新聞
国土交通省/上下水道在り方で1次取りまとめ案
国土交通省の「上下水道の基本的なあり方検討会」(委員長・滝沢智東京都立大学特任教授)は10日都内で第5回会合を開き第1次取りまとめ案を議論した。上下水道を「最重要インフラ」と位置付け「将来にわたり適切な事業運営が可能な組織体制の再構築と更新投資の財源の確保」を喫緊の課題に据えた。「強靱で持続可能な上下水道」を実現するため経営広域化の国主導による加速、適切な更新投資と次世代に負担を先送りしない経営へのシフト、官民共創による上下水道一体的再構築と公費負担の在り方検討の三つの基本的方向性を示した。情報元:建設工業新聞
▽2025.6.10
内閣府/民間資金等活用事業調査費補助/支援対象6件決定
内閣府は2025年度民間資金等活用事業調査費補助で道の駅おがち再整備など6件を採択した。公共施設のPPP/PFI導入可能性調査やデューデリジェンス等に対し原則1000万円(政令指定都市は500万円)を上限に補助し自治体の官民連携を後押しする。情報元:建設通信新聞
▽2025.6.9
政府/新しい資本主義実現会議/実行計画改定/BIMによる建築確認
政府の新しい資本主義実現会議は賃上げや投資促進などに関する実行計画2025改定版を決めた。産業政策のうち「建設・都市DX」は、BIMによる建築確認、都市などの3Dモデル「プラトー」の拡大と海外展開を進める。「建設業の働き方改革」として必要経費の確保や支払い、価格転嫁対策、建設Gメンの体制強化などに取り組む。中小企業支援の一環で、低入札価格調査制度と最低制限価格制度の導入や活用を進め、状況を可視化する。建設キャリアアップシステム(CCUS)を参考に技術や技能、経験を処遇につなげる仕組みの導入を進める。情報元:建設工業新聞
▽2025.6.6
PFIの指針改正/対価改定基準を明示
政府は4日、民間資金等活用事業推進会議を開きPFIに関する各種ガイドラインを改正した。サービス対価改定の基準時点を実施方針などに明示する必要性を示し、物価指数は民間事業者との協議で決めるとともに適切な物価指数の選択が難しい場合でも丁寧に検討するよう求めた。急激な物価変動に対応し民間事業者が適正な利益を得られる環境を構築するため契約に関するガイドラインとPFI事業実施に関するガイドラインを改正した。民間のノウハウをより活用するため官民双方の留意点も追記した。情報元:建設通信新聞
対象自治体5万人以上に/PPP/PFI優先的検討規定
政府は4日、PFI推進会議を持ち回り開催し、「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」の2025年改定版、PPP/PFI関係ガイドラインの改正を決めた。PPP/PFIの導入を優先的に検討する規定の策定・運用を求める地方自治体を従来の人口10万人以上から5万人以上に拡大する。検討対象の事業を柔軟に設定することも盛り込んだ。地域の課題解決に官民の連携が求められ、人口10万人未満の自治体でもPFI事業が増えている。2025年改定版の優先的検討指針は、優先的検討規定を運用する対象自治体を増やし、PPP/PFIの普及を促すことにした。改定では、PPP/PFIの導入の検討開始時期に、分野横断型・広域型の案件形成を追記した。事業化を目指す中で、コスト面だけでなく、民間提案や官民連携によってもたらされる多様な効果を評価することの重要性を強調した。情報元:建設工業新聞
▽2025.6.6
PPP/PFIアクションプラン/自治体の支援強化など/政府、年改定版を決定
政府のPFI推進会議(会長・石破茂首相)は4日、「PPP/PFI推進アクションプラン」の2025年改定版を決定した。地方自治体の支援強化、民間事業者の事業環境改善などを課題に挙げた。対策として、検討期間の短縮と手続きの効率化を目的としたマニュアルを年度末に作成する。水道、下水道、道路、公営住宅、自衛隊施設など重点分野について年度までに650件の事業化を目指す目標は、年度末が209件となり、進捗率は%となった。順調な進行と捉え年度は受発注者が直面する課題への対応を進める。自治体の支援強化では、煩雑な手続きや検討期間が長いことで事業化の検討が敬遠されたり、小規模事業に民間の関心が集まらなかったりするケースがあるため、検討の期間を短縮するポイントなどをまとめたマニュアルを整備する。情報元:建設工業新聞
PPP/PFI行動計画を改定/優先規定規模5万人に拡大
政府は4日、民間資金等活用事業推進会議を開き、PPP/PFI推進アクションプランの2025年改定版、多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針の2025年改定版をそれぞれ決定した。指針ではPPP/PFIの導入を促す自治体を広げ、PPP/PFIの優先的検討規程の策定を求める自治体の人口規模を現行の10万人以上から5万人以上に広げた。アクションプランではPPP/PFIのノウハウが不足する自治体の支援に力を入れる。民間資金等活用事業推進機構の伴走支援体制を強化するとともに、事業の検討開始から事業契約までの期間短縮化、手続きが効率化できるポイントをマニュアルにまとめ、2025年度末に公表する。情報元:建設通信新聞
▽2025.6.3
国交省/7月28日にPPP推進へ官民対話/案件6月18日まで
国土交通省は、PPP/PFI事業の推進に向けて、自治体と民間企業とのサウンディング(官民対話)を7月28日に実施する。自治体に対してサウンディングの希望案件を18日まで募集する。募集対象は、事業発案や事業化、事業者選定を検討している案件。20件程度を選ぶ予定。
7月中旬までに応募案件を公表するほか、助言を行う民間企業を募集する。サウンディングは11月も実施する。
情報元:建設通信新聞
国交省/PPPパートナーに新規12社で79社認定
国土交通省は、PPPパートナーに79社を認定した。新規は12社。自治体、企業向けのセミナーや個別相談などを通じてPPP/PFIの普及に取り組む。内訳はデータベースパートナーが3社、セミナーパートナーが8社、金融機関パートナーが15社、個別相談パートナーが60社(重複含む)。
新規のパートナーは次のとおり。
▽オープン・エー▽アジア航測▽アプレイザルジャパン▽クボタ▽五星▽ザイマックス▽日本管財▽日本工営▽パシフィックコンサルタンツ▽パスコ▽復建調査設計▽フクシ・エンタープライズ。
情報元:建設通信新聞